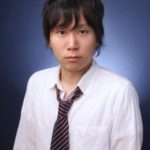こんにちは、シンガーソングライターの山田啓太です!
Twitter→@PON1240
あなたはダイヤトニックコードという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
それは、作曲をする上でとても大切なことになります。
難しそうと思う人もいるかもしれませんが大丈夫です。
なるべくわかりやすく説明します。
その前に、ダイヤトニックスケールについて、少しお話します!
もくじ
ダイヤトニックスケールとは
「ダイアトニックスケール」とは基準の音から「全音・全音・
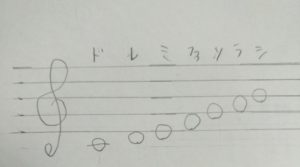
↑これが、キーをCとした時のダイヤトニックコード
ダイアトニックスケールについては、
この、「ドレミファソラシド」それぞれの音をルートにして、
コードとは
複数の音を同時に鳴らすことです。和音ともいいます。
Cコードなら、ド、ミ、ソの3和音になります。
ルートとは
コードの中の一番低い音のことです。
根音、ベース音ともいいます。
先程のCのコードなら、ルート音はドになります。
では実際のダイヤトニックコードの作り方をお話します!
ルートに対して3度の音を加える
「全音・全音・
このルート音に、ルートに対して3度の音を重ねます。
ルートの隣の音は2度で、
たとえば、ドに対して3度の音は、ミになります。
重ねるとこんな感じです。
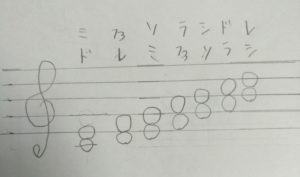
↑ルートをCとした時のダイヤトニックコードに3時の音を足すとこうなる。
ルートに対して5度の音を重ねる
先程と同じ考えです。
ルートの、4つ隣の音が5度です。
先ほどの、3度の音の2つ隣のででもありますね!
例えば、ドに対して5度は、ソになります!
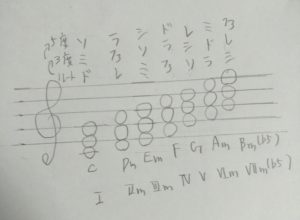
↑さっきの3度足したものに5度の音を足すとこうなる。
これをコードにして表すと
C、Dm、Em、F、G、Am、Bm(♭5)、
これが、「ダイアトニックコード」です!
ちなみに、C、Dm、Em、F、G、Am、Bm(♭5)はローマ字を使って表すこともあります。
そうすると、Ⅰ、Ⅱm、Ⅲm、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵm、Ⅶm(♭5)
この3つの音で構成されたコードを「三和音」
ここに、5度の2つ隣の音「7度」を更に重ねると、
「四和音」のダイアトニックコードになります。(「テトラッド」
まとめ
今日の記事はいかがでしたでしょうか。
ダイヤトニックコードの仕組みは覚えてしまえば簡単ですよね!
・基準の音から「全音・全音・
・ダイヤトニックスケールの基準の音がドの場合ドレミファソラシドになる。
・そのドレミファソラシドはルート音となる
・ルート音に3度と5度の音を重ねるとダイヤトニックコードとなる。
最後までご覧頂きありがとうございました!